
Audiokillar
第二章 ROCK・父への誓い
「お父上が死亡したことによりレナード大統領はジョシュに決まりました」
グレーの髪に角張った輪郭の顔、目元の涼しい執事のロバートがコーヒーと朝刊を持ってきた。新聞七紙をとっていた父がいつも最初に手にするのがニューヨーク・タイムズ。
父が座っていたデスクの椅子に、今はオレが座っている。左側の窓からはニューヨークの街並が見下ろせる。
朝もやに煙る自由の女神は、まるで泣いているようだ。
この女神を見ながら、父はコーヒーを飲んでタバコを吸っていた。
あの父のシルエットが今、オレと入れ変わっている。
引き出しを開けると、赤のラークが入っていた。父のマネをしてくわえてみた。ロバートが火をつけてくれた。こんなことにさえも、とてつもない愛情を感じた。
「有り難う」 「いいえ」
一八歳になったばかりのオレに静かに一礼するロバートに、 父の大きさと力を感じた。
「ロバート、何か父の話をしてくれないか……」
「はい……カルビン様は医療や福祉に力を入れられておりました。ゲーリー前大統領にいつも進言していたのも彼と、 そして同志のアンソニーです」
「テロめ……許さない」
握りしめたニューヨーク・タイムズ……その裏に見え隠れするのは中近東の新国家インダス連邦の巨大な黒幕だった。怒りと憎しみに流されそうになる心を、ロバートの言葉が遮った。
「確かに、憎むべき犯罪です。しかしなぜ彼らがテロを起こすのか、その原因を究明しなければ、いつまでたっても解決しない…… お父様はいつも、こう言っていました」
テロに理由などあるものかと、少し前までの自分なら怒鳴っていただろう。しかし、今のオレは闇の中でうごめく、巨大な憎しみを感じていた。 オレだって政治家になったら、同じように命を狙われていたのだろう。
勝ち誇ったように、手を上げるジョシュの写真さえも、哀れに見える。彼だっていつテロに殺されかねない。
怖い……。情けねえくらい怖い。
父はこの恐怖とも戦ってきたのか。
オレは命を捨てても何か懸けられるものがあるだろうか……。
父の跡を継ぐ……? 本当に出来るのか……。
世のため人のためとはいえ、命を狙われてまで政治家をやる価値が、オレにとってあるだろうか。父が残した言葉が、いつまでも心にひっかかる。
父は最後、ロックをやれと言った。自分のようにテロの被害に遭って息子を死なせたくないという思いだったのか。どうせ命を懸けるなら、ロックに懸けたいと父に言った。
そうだ、ロックをやっている最中なら、撃たれて死んでも悔いはない。
俺にだって命を捨てても懸けられるものがある。
「父さんの言っていた言葉の意味を知らないか。ロックをやるんだって……本当さ、それから…… オーディオキラーと言っていた」
「キアヌ様、その前に、あと三人集めろと仰いませんでしたか」
「そう言えば……なぜそれを知ってるんだ?」
「オーディオキラー、お父様は、あなたにこのバンドのリーダーとなって 世界平和のために戦って欲しいと、兼ねてより仰っていました。 これは私と、もう一人、あの男しか知りません……」
ロバートと視線が重なった。それだけで、言おうとしていることや 何を聞きたいのか、すぐに彼には分かる、そんな二人の仲だった。
「こちらへおいで下さい」
ロバートに導かれるまま、かつて父しか使用しなかった地下室へ案内された。
薄暗く、狭くて長い廊下。ダークブラウンの壁の左右一杯に彫り込まれた本棚。無造作に詰め込まれた書籍を見てみると、左右に斜めに倒れたものばかり。いかに頻繁に取り出されていたかが分かる。
200カ国以上の国の情勢がわかる莫大な量の書籍。母国レナードはもとより、隣国カナダ、メキシコ、遠くはイギリス、ヤマト、中国……。
この十年の間にレナードは五つの国を侵略し征服した。キューバ、アフガニスタン、パキスタン、ネパール、バングラデシュ。 ヨハネの黙示録を読んだばかりのオレは、このままレナードが世界崩壊への道を 突き進んでいくような不安に駆り立てられイライラすることがよくあった。
そして核爆発にさいなまれる我が肉体が、夜毎見る夢を支配する。
それを吹き飛ばしてくれるのもロックだった。高校の受験でさえ生ぬるいものに思えてくる父の書斎。
父の抜け殻となった館を、 オレはただ歩き続ける。
行き止まりの、ドアの取っ手は鮮やかな金。
ドアをあけた瞬間、オレは我が目を疑った。
目に痛いほど輝くシンバル、中央のスタンドマイク、そして左右に立てかけたギターと ベース。右側のグレイのソファに座っているのは誰だ……。
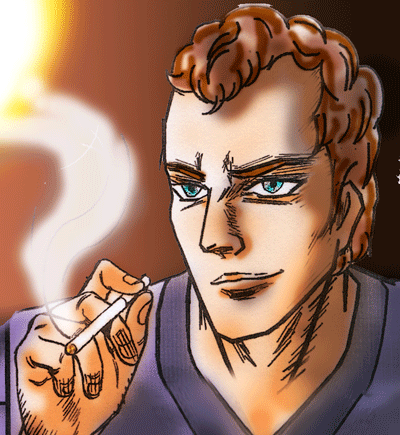
「やあ、君にどうしても見せたいビデオテープがあってね」
Vの字に渋く禿げた頭に薄い金髪が無造作に額にかかっているが、顔はかなりの 伊達男だ。クッキリした目と彫りの深い鼻筋はハリウッドでもいけそうだ。
壁際の51型液晶テレビが、暗がりに光を放った。
いきなりの大音量は、懐かしくもあるバンドのサウンド。ギターを片手に歌っているのは父だ。
「これは……」
20年ぐらいも若返った父のギターの弾き方はオレにそっくりだ。それだけで胸に詰まった涙が溢れ出た。サビの部分では、少しためて一気にダウンストローク、よけいなメロディーを 入れないでヴォーカルを際立たせている。
そしてギターの出番が来た。
アルペジオから始まって、独自の転調、ドッペルドミナントを入れている。
「凄い、ギターがヴォーカルの抑揚をさらに盛り上げている…… でもこのロックは聴いたことがない、オリジナルか……」
「そうだ。彼の横でギターを弾いているのが私だ。スコット・トレモンティ、 またの名をケビン・レノン。よろしくな」
彼が手を差し出し、オレはしっかりと握手した。
「ケビン・レノン……まさか同姓同名?」
「いいや、多分君の最初に疑った線だ」
「そんなバカな! ケビン・レノンは暗殺された筈だ!」
「君のお父さんに、ずっと匿って貰っていたよ。 あー、それからなんだ、そのケビン・レノンってのはやめてくれ。 スコット・トレモンティってこれからは呼んでくれよ」
「スコット・トレモンティ……分かった、 ところでストット、あなたは何かを知っているのか。オーディオキラーって何なんだ」
スコットはグっとかみしめるように、目を閉じた。そして目を開けると、 今度は力強い視線をオレに返した。
「今はまだ、君が知るべき時ではない。君には、世界最強のバンドを作ってほしい。 そして、世界中で歌って欲しいんだ」
「なら聞かねえよ……。やるさ。それが父の意志なら、 ロックを引きとめる鎖はもうない。タバコもやめるよ」
この時、ロバートとスコットがオレを見た。
「学校のバンドメンバーを紹介する。明日のライブに来てくれ」
* *
高校最後の学園祭ライブ。
ポップコーンやソフトクリーム、ハンバーガーショップが立ち並ぶ校門入り口。
ニューヨークの朝は冷え込みが厳しく、模擬店の友達は売り上げを心配していたが、 昼になると夏の日差しが戻ってきたように乾いた太陽が大地を照りつけた。
ノドの渇きをいやすためメンバーにペプシを4本買って地階の練習スタジオへ戻った。
我がニューヨークハイスクールは、バンド部の活動も盛んで練習スタジオも3つある。
出番の1時間前に最後の練習が許される。
我がバンド名はグレードアップ。
どこまでも成長していきたい思いで、オレが名付けた。
ヴォーカルのマトスはメンバー1のハンサムで歌唱力もある。
ベースのポールのテクニックはプロ級。
ドラムのアダムはパワーヒッター、 スティックで5回もスネアを破ったことがある。
みんな、この高校3年間で 100回以上のライブを共にした。
みんなかけがえのない戦友だ。
「マトス、声の調子はどうだ」
「絶好調さ、キアヌ将軍」
メンバーはオレのことを将軍という。射撃の腕がたつ事とケンカが強いこと、そして頼りがいのあるということもあいつらの視線には込められているから、 このニックネームも悪くはない。ただそこには、頑固で言い出したら聞かないという皮肉の意味も、入ってはいるが……。
「絶好調にしては声が出てねえぞ。そんなんじゃ女も口説けねえぜ」
「あいにく俺はお前と違って、もてるんでね」
マトスはオレの肩を掴んでニヤリと笑った。
「もう薬は止めてるんだろうな」
急に、その掴んだ肩を突き離しやがった。
「やってないって。オーバードーズで死んだヤツらの二の舞いは踏みたくないよ。 あいつの怖さは俺が1番知っている。それにお前は薬をやめさせるためにマフィアとまで ケンカしてくれたんだ。そんなお前を裏切ることはできないよ、キアヌ将軍」
オレはホッとする気持ちと、まだ止め切れていないんではないかという疑いを半分持ったまま、今夜は彼を信じることにした。
「今夜は、最高にセクシーなライブにしてやろうぜキアヌ」
「そうだな、頑張ろう」
次にドラムのアダムが気になった。リズムが単調なのを指摘して 新しいオカズを入れたりしてまだ日が浅い。もたつきが気になる。
「おい将軍、お前の言っていた新しいリズムはやっぱちょっと難しいぜ。 変にプロぶって行かなくてもいいじゃないか。俺たちらしくオーソドックスで行こうぜ。今までの叩き方でも十分にウケていたじゃないか」
アダムはスネアとシンバルを叩きまくる。バスドラの皮がブルブル痙攣してシンバルが 耳をつんざきオレのハートを揺さぶった。最後にポーズまで決めニヤリと笑いやがった。
「お前はカッコばかりつけて無駄な動きが多いんだよ、それだったら、ちょっと変更する ぐらいの余裕はあるだろう!」
「将軍、追求していきたい気持ちは分かるが、妥協点も必要だぜ。 確かにお前がこのメンバーで技術が一番抜け出ていることは分かっているよ。みんなもお前に追い付くように頑張るからさ、今回はよお、これで行こうぜ頼むよ」
ベースのポールもやれやれとあきれ顔でつぶやいた。
「あんまり難しいこと言うなよキアヌ、それがお前の悪いところだ」
マトスが汗ばんだTシャツを着替えながら、新しいシャツから顔だけを出してお化けのふりをしている。みんなの笑い声が、熱くなった頭を覚ました。
「分かったよ。無茶を言って悪かったな、みんな」
ステージでは、バンド演奏が12時から夕方6時まである。オレたちの出番は、5時からたっぷり1時間。練習時間も特別に2時間取った。
「彼女も見に来ているんだ。今日は絶対に失敗できないぜ」
メンバーたちは、彼女の話でもちきりだ。オレを除いては……。
「さあ、気を引き締めて練習をやるぞ」
昼も夜も分からなくなるスタジオから出てきてオレは、夕方になったことを実感した。 それでも校庭は賑わいでいる。ソフトクリームを右手に持ったスコットとハンバーガーにかぶりつくロバートを 見つけた。
そしてもう1人、何処かで見たことがある顔ぶれがいた。
音楽情報誌に載っていたレコード会社『ランナー』スカウトマンのジョニーだ。レナード合衆国チャートにランク入りするアーティストを3人もスカウトしている。まさかロバートがこんな手はずを整えてくれていたのか。
このことはメンバーに話すべきか。
いやヴォーカルはプレッシャーに弱い。他のメンバーもドラムのアダムが力むと余計なアクションを入れて カッコつけたりしそうだ。それにつられてポールも乱れる。それよりは、このステージを楽しませた方が、あいつらの力も出せるはずだ。
ここはみんなに黙っておくか。
オリジナルは50曲はある。今夜の学園祭はその中でも特にお気に入りの10曲だ。 ロックだけには絶対の自信がある。
このステージから一気にプロデビューだ。
遠くの人混みにキャサリンを見た。
あの事故から、2人の関係は冷え切ってしまった。互いに、嫌いになった訳ではない。
ただ、かみ合わなくなった。心の中に、焼き付いた残像があまりにもリアリティーに蘇ってしまう。
彼女の、さなぎから蝶へ脱皮した瞬間があまりに強烈過ぎた。 その直後に両親を飲みこんだ瓦礫、血、テロへの憎しみが混同して今でも感情のバランスが取れなくなる。
キャサリンからハンドルを奪いオレは無免許で暴走し、彼女に怖い思いをさせた。 車も傷つけたが、それ以上に彼女の心を。
逃げ出したい、忘れたい記憶の中に、彼女も一緒にいた。
そして心の傷をいやすものは、音楽への情熱。 心の中に占める彼女の存在を遠ざけることで、あの痛みからも逃げようとしていた。 そしてどこまでも膨れあがる夢が、彼女と触れ合う時間を邪魔した。
声をかけたい……もう一度やりなおしたい。
そんな一瞬の切ない思いもプロデビューという大きな炎に飛ばされていった。今日のライブは絶対成功させなければならない。この高校から一気に、世界に羽ばたく。こんなところで、グズグズしてなんかいられないんだ。
ついにオレたちの出番だ。
夕暮れのステージには照明が当たり、青と赤のグラデーションがオレたちの空間を 演出し始めている。マトスの顔は青白く燃え、いつものように自分に気合いを入れるべく 頬をピシャリと叩くと、オレに言った。
「キアヌ、この三年間の高校生活で最高のライブにしようぜ。
今まで、ありがとうよ……」
その言葉に火をつけられた。
そんなこと、言うガラじゃないくせに……泣けるぜ。
「キアヌ、俺たちお前のおかげでここまで来れたんだよ」
アダムだった。オレがマフィアとやりあうとき、こいつだけが一緒に来やがった。ドラム好きは殴ることが好きな奴が多いんだとか言いながら。
「キアヌ、実はよ、ちょっと早いが、お前の誕生日に買ったギターがあるんだよ。 ちっと高いからみんなで出し合ったんだ。エリックモデル、こいつで弾いてくれ」
ポールがケースから黒いギターを取り出して俺に手渡した。
「お前ら……バカだぜ……」
涙があふれた。何て奴らだ。いつも口うるさいオレを……ちきしょう。やってやるか! メンバーはステージに駆け上がっていく。どさくさに紛れてこんなところでバースディプレゼントなんて、晴れがましいことが大嫌いなあいつ等らしい。
ステージから客席に手を振るメンバーたち。
オレは最後に、この新しいギターでステージに駆け上がった。 学園の盛り上がりは最高潮に達した。
演奏が始まる。
マトスが麻薬の匂いを醸し出すハスキーボイスでシャウトすると学生たちのハートに火がついた。この高校の女生徒の半分が彼のファンだ。
”オーベイビー、濡れた唇はレッドファイアー……
黒いその瞳は、俺を狂わすブラックファイヤー“
そう、キャサリンの好きな曲、ブラックファイヤーだ。
ダイナマイトのような激しいロック、一転して涙のバラード。この二曲で会場はグレードアップ色に染まった。アダムのバスドラはツインペダルでドスドスと会場の心拍数をつり上げた。 ポールのベースが背骨を振動させる。
オレは回りの音を調和しながら、ギターをグレードアップ色のサウンドに仕立て上げた。揺れる、燃える、高校3年間を融合したオレたちだけの音。
最後の夏に爪跡を残すべくオレはギターリフを刻む。
一時間の本能がようやく燃え尽きた。
空はパープル、祭りのあとは後片付けでにぎわった。
オレはそんな人混みの中にロバートとスコットの姿を追いかけた。
この人だかりに埋もれて、騒がしくなって先に帰ったんだろう。
2人とも人込みはあまり好きではないし。
マトスは女性ファンに囲まれ、サインをしている。オレはメンバーたちと一緒にプロデビューできることを確信した。
* *
気がつけばエルメスのクロノグラフは深夜の二時を回っていた。
伝統を受け継ぐコダワリのデザイン、オレのお気に入りの腕時計だ。打ち上げパーティーで飲んだお酒は、ほろ酔い気分を自宅にまで届けてくれた。
屋敷の中の見慣れた景色までもが希望に満ちていた。応接間のソファに身を投げ出し未来の自分を想像した。
ノックもせずにドアが開いた。
スコットがしかめっ面で立っている。
「そんな顔をするなよ、まだ未成年だろっていうんだろう。本国では、二年前から飲酒は19歳から許可されることになったんだっけ……? アハ、まだ18だった。でもよ、そんな法律を守っている奴なんて、 今時こんなレナードにいないさ。今日は、大目に見てくれてもいいだろ」
ムスとしたスコットがケンカ口調で言った。
「私は中学で毎日ウイスキーを飲んでいたよ、このハゲかかった頭が、そのせいかどうかは分からないがな」
「? なに怒っているんだよ」
「結論だけ言うと、不合格だ」「なにが……?」
「おまえのバンドではAudiokillarは起動しない」
水でもぶっかけられたように酔いが覚めた。この一言で。
「まずヴォーカルが最悪だ。声が汚い上に声量も足りない。 そのうえ、キーまでしっかりしていない。つまり、救いようがないという事だ」
「何だとお……!」
「ジョニーでなくとも、あのレベルなら私でも願い下げだ。とてもスカウトする気にならない。ドラムは一本調子で工夫が足りない。ベースはノリが悪い。
ただひとつ、お前のギターテクニックと、楽曲のセンスだけはいいとジョニーは言っていたよ。ギターのビオンディが脱退したブリッツが新しいメンバーを探している。 お前を引き抜きたいと言っていたがどうする」
「ブリッツのロックに興味はないさ。サウンドはオーソドックスすぎてギターはバッキングしかしてない。あんなバンドのメンバーになるくらいなら、 一人でいた方がマシさ」
「理想だけは高いんだな、だが今のお前たちをプロとして認めてくれるところはないぞ」 「待てよ、みんなでプロになるって誓ったんだ! そんなに簡単に諦められるか! マトスとはガキの頃からずっと苦労してきたんだ!」
「そんなもの関係ない、下手は下手だ」
「ずっと今まで一緒にやってきたメンバーの絆が、お前に分かるか!」
「リスナー達はおまえ達の絆を見たいんじゃない。いい曲を聴きたいんだ」
ズバリと言ってくれやがった。ずっと、ベールをかぶせてきた傷口に、ピッタリ形の合う剣を突き刺された。
本当は分かっていたんだ。
オレが一番わかっていたんだ。
「だけど皆若い。これからどんどんうまくなるさ。オレが引っ張っていくんだ!」
「思い上がりもいいかげんにしろ! お前が引っ張っていくほど、お前のレベルは高くない。お前は引っ張られる方だ。プロを目指すとはそう言う事だ」
バンドマンでもある彼の言い分は確かに、その通りだ。
急に、体中の血が引いて地面にでも流れ落ちたぐらいの冷や汗が出た。
「ヤンキースタジアムの大実験を知ってるか」
「知ってるよ。あんたが暗殺された1番の理由は、あれをやったからだ」
スコットはニヤリと笑ってオレに腕時計にみたいな黒いバンドを見せた。
「エモーショナルバンド、エモバンドだ。オーディオキラーの能力を最大限に 発揮するにはこのパラメーターが、500以上ないといけない」
「ああ、知ってるよ」
「こいつは耳のいい機械でな。エモーショナルエナジーを数値に換算できる。
つまりだ、こいつに出てくる数値はいい音楽を聴いた時に感動する人間のエモーショナルだ。あの伝説のバンド、ブラスターのメンバー4人はこの数値が500を超えた」
黒い腕時計のような、ゴツいバンドは俺を挑発するように、不気味に光る。
「どうだ、お前もこのバンドをつけて、1曲演奏してみるか。
それともそんな度胸はないか?」
「やってやろうじゃないか。売られたケンカは買うのがオレの流儀だ」
いざ巻いてみると、右の手首に金属の冷たさがズシリとくるエモバンド。
父の地下スタジオ。父の使っていたであろギターアンプに父の形見のギターをつなぐ。
「サウンドスレイブの名曲『キス・オブ・ナイトブルー』は弾けるか」
「あれなら十八番だ」
「よし、やってみな」
グレードアップでは頭ひとつ抜けているオレの腕だ。これで400を越えなければバンドメンバーの腕はさらに落ちる。 とてもプロレベルではないと諦めもつく。
ダウンストローク、そして一気に小刻みなリフを刻む。
ライブをやったばかりのオレの指は冴えた。プロでも技術を必要とするこの曲を、ガキの頃から弾いてきた。この曲に懸ける思いは誰にも負けない。
スコットもニヤリと笑った。
その青く鋭い目を見つめ返しながら、これでもかとオレのギターテクニックを披露した。本物と比べてもわからないくらい、オレのギターは泣き叫んだ。音符のどれをとっても、寸分の狂いもなく、嵐のような曲を最後の1音まで、完璧に引き上げた。
指先に心を込めて…… 弾いた後には、やり終えた充実感と余韻に浸った。
「どうだスコット」
「答えはエモバンドに聞いてみなよ。この楽曲におけるお前の、エモーショナルエナジー、平均数値が出てるはずだ」
「なに……」
オレは右手首の、点滅している赤いデジタル数値を見た。
355……!
「そんなバカな……」
「バーカ、お前の腕なんてそんなもんだ。分かったか。 グレードアップのメンバーなんてせいぜい200ぐらいだ。 そしてお前は、オーディオキラーのメンバーにもなれない。 たいしたことない男だな、キアヌ・クルーガー」
スコットは堂々と言い下した。
「待てよ……オレは親父に誓ったんだ。オーディオキラーの リーダーになって世界平和のために戦う……」
「関係ない。そんなのはお前の個人的な事情だ」
「だから待て! バンドを作るっていうことはオリジナルだろ! オリジナルで勝負しなきゃ意味がないんじゃないのか! そしてもうひとつ!」
大きくため息をついて、ギターを置いた左手はタバコに火をつけていた。
「あんたが他のギタリストを探し回ったところで、命を捨てて レナード軍と戦うヤツが何人いるっていうんだ」
振り向いたスコットがニヤリと笑った。
「お前は本当に命を懸けられるって言うのか」
根元まで吸ったラークを灰皿に捨て、オレは立ち上がった。
「マフィアとは相手が違うぞ、キアヌ」
「そんなのは100も承知だ。いいか、覚えておけ、オレは出来ないことは言わない。 オレをメンバーにしろ、ロックに命を捨てることは出来る。もう1度、いや何度でも挑戦して必ず、 エモーショナル、500を超えてみせる」
スコットは何も答えず、じっとオレを見つめている。
どう解釈したらいいか分からない瞳だが、オレはただ、 ギターを弾くだけ。
この胸の奥に燃える炎は、こんな曲しか表現できない。 うなるディストーション。 そしてマイクを握りしめた。
BLAZING RED
燃え盛る火の消える時まで
戻れない 消せはしないさ
遥か地平を焦がす太陽
死を前に何故に輝く
何処へ行くのか 人の心は
激流に押し流されて
狂った社会 機械のように
踊らされクズになるまで
赤い炎が叫ぶ夜 人は夢に帰る
我がための 夢がための命
壊せ全てをBLAZING RED
*Don’t stop go your own way!
You’ll get ambition!
終わりなど在りはしない
逃げてゆく夢 永遠に追う 星の光の様に
死の宣告を夢が下した
時は無い 無駄にできない
掴んだものは過去が飲み込む
走れるだけ走るだけさ
時代(とき)に革命を起こして新たな時代が来る
誰にでも心にある炎
燃やせ命をBLAZING RED
Don’t cry until you achieve−
your big ambition!
遮る全てを砕け
I’ll be the king some day!
Don’t lose your ambition!
Don’t stop go your own way!
曲が燃え終わった。
グレードアップでは1度もやったことのないオレだけの歌。
2カ所も間違えてしまった。なのに、悔いはまったくない。 胸の奥から沸き上がる熱い感動で、心が震えていた。
「お前のオリジナルか」
スコットの目つきはさっきと変わらない。
「ああ、嫌いか」
「いいや……良かったぜ。エモバンドを見てみろよ」
腕時計でも見るように赤いデジタルに目をやった。
500……
「マ……マジかよ……おい、スコット!」
オレの声は飛び跳ねた。
「まあ、そういうことだ。エモーショナルパラメータってのはなあ、 テクや難易度だけを基準としない。あくまで、感動なんだよ」
「感動……」
「不覚にも俺まで感動しちまったよ。おまえはギリギリ合格だ」
「ホントか、やったぜ!」
父との約束に一歩近付いた。喜びが全身にあふれた。
「もう分かっただろ、あのバンドじゃダメだってことが。お前には本物をやって欲しいんだよ。チャラチャラしたアイドルバンドで終わってほしくないんだ。分かるか」
なぜだろう。悔しい。だけど……嬉しい。
本当はオレも、もっと追求したかった。
バンドのリーダーでありながら、すれ違いを感じていた。
「私は死んだ事となってからな、この7年の間に世界中を旅した。凄い男が三人いるよ。バンドは四人が同じ力で初めて輝く。お前のギターはいいが、あとの三人はダメだ。売れたとしてもすぐに消える。そしてお前は音楽を追求したいんだろう? 今のバンドでやっていける訳がない。 私が見込んだその三人をバンドに引き込むんだ」
忠告というのはとても損なことだ。痛いところを突かれると、誰だって頭に来る。
だけど本当は忠告こそ人を成長するものなんだと、 それぐらいは若いオレでも分かる。 特にロックに関しては彼が正しいことを言っていることも分かる。
友情ゴッコだったかもしれない。
グレードアップが今までかかって築き上げた城が、土台から崩されていく。
「……分かったよ、やってみるさ」
あいつらが、プレゼントしてくれたギターを、オレは静かに置いた。
今まで……有り難うよ。マトス、アダム、ポール。
この日が、オレの卒業式だった。
四カ月も早い……本当の意味での卒業式。
その次の朝、キャサリンに手紙を出した。
キャサリンへ
君より1日早く、オレは明日18になる。
明後日は君の誕生日だね。 おめでとう。
君にとって素晴らしい歳であるように。
オレは明日、メンバー探しの旅に出る。
いつ帰ってくるかわからない。
君を好きな事に変わりはない。
だが今は、それ以上に自分がしなければならないものがある。
今までのメンバーでは限界がある。
勝手な男だから待ってくれとは言わない。
今度会うときはステージでの再会を約束するよ。
そしてその時まで、お互いの気持ちが変わらなかったら……
また君の恋人として、会えなかった月日の空間を埋めたい。
今までありがとう。 また逢う日まで
キアヌ・クルーガー